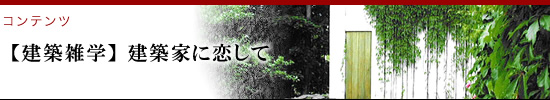
―『キヨシ』・・・プロフェッサーアーキテクトとして ―
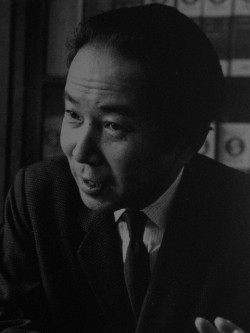
一方の池辺[以後キヨシと表記]も戦後モダニズムの建築家として住宅建築を
リードしたひとりです。キヨシとその研究室(*1)の仕事は、エコロジカルな考え方、
デザインの枠を超える思考の在り方が読み取れ、現代にも充分通用する先見性を
持って仕事をしていました。小住宅の設計を通じて、機能主義理論に検証を加える
手法を取った建築家の代表がキヨシであると言えるでしょう。
東京大学に席をおくプロフェッサーアーキテクトであるキヨシは、古い住宅概念を
打破し、機能主義理論に基づく新しい住宅像を提示し「立体最小限住居」を含む、
Noシリーズと命名された一連の試作小住宅(*2)をモーレツな勢いで手掛けて
いったのです。ナンバリングで呼称された彼の作品は系統的な思考法で創作される
ために追跡するテーマも明確です。キヨシが目指したのは工業化された建築であり、
建築をモデュールで構築していくことであると言えるでしょう。
長い歳月をかけ70件を越える建築を手掛ける中で徹底した寸法体系論を磨き上げ
GMモデュール(*3)として発表しています。
常に理論的な立場から建築を組み立てることを模索し、当時、まったく新しい建築を
作り出そうとしていたのがキヨシであったのです。池辺研究室出身の難波和彦氏の
回想ではデザインに対して徹底して合理的で、美学的なアプローチを嫌い、
プロポーションやバランスよりも性能や工法を優先することを求めたといいます。(*4)
しかし実は非情にセンスの良い芸術家肌の建築家であったことも指摘されています。
ただ大学の研究室に籍を置くものとして、また戦争を体験し圧倒的な工業力で敗戦した
事実を目の当たりにしているキヨシ世代は時代のニーズとして工学、工業化を優先
せざるを得なかった部分があると同時に工業化に対する夢と希望もあったのでしょう。
(*5)また当時の思潮として美学を求めることは、戦前の様式主義に囚われ、
観念的な方向へ引きずられる事を懸念したのではないかと思われます。(*6)
決して芸術的なこと、美学的なことを排除した訳でなく、工業化に基づく機能主義理論
の先に新しい美の感覚、芸術性が潜んでいることに期待していたに違いないと
思うのです。
それを求めていく行為(システム)こそデザインとして捉えていたふしがあります。
そしてキヨシは住宅という名の建築を通して何を追及しようとしていたのでしょうか?
もともと池辺は住宅作家なのでしょうか?
藤森照信氏は著書(*7)の中でこのあたりを紐解いています。1943年の在盤谷
日本文化会館コンペに始まり戦後の数々の国家的な事業(*8)を担当し、7つ年上
で大学の先輩・丹下健三と同じ道を行くように思えたはずが「立体最小限住居」を
ひとつの境として住宅建築に傾倒していきました。何故でしょうか?
藤森氏は新人バッターが初打席でいきなりホームランをかっ飛ばしたという例えで
表現し、それが影響した!?と。明確な結論は出ていないが恐らくそんな単純な
理由でもないと思いますが・・・。
そのようなことはきよしも同様で他の建築家にもいえる事であります。
キヨシもこの時期、国家的プロジェクトとは別に在野の建築家として一般市民の目線
の建築を作らなければならない事を感じていたと考えたらどうでしょう。
それには住宅しかなかったのでは。
モダニズム運動の背景には産業革命以前の封建社会から一般市民を中心とした
民主社会への移行という大きな社会的な流れが源流にあり、モダニズムを志向した
建築家も権威を象徴する国家建築家像から一般市民のための生活空間を提供する
市井の建築家像への変化がその根底にあったはずです。
モダニズム建築は人間生活を大切にする事を本懐とするはずが、その後の社会の
潮流から経済至上主義の象徴といった位置付けにすりかえられてしまった
観があります。ここにモダニズム建築の悲しい一面が見えるのです。
キヨシは「立体最小限住居」という一作でこの齟齬を早々と読み取り、あえて丹下と
同じような道を歩く事を拒否したんじゃないでしょうか。常日頃から「住み手が家と
格闘するような家をつくる」と公言していたキヨシであるが、それは人間の住生活と
いうものの限界を知るためであったと思います。コンクリートの供試体を潰して限界を
知るが如くどれだけ小さくできるのか、ドアを付ける必要があるか、窓を開ける必要が
あるかなどを追求したわけです。それはあくまでも実験であり、個々の住宅がそれぞれ
完結した作品といった概念は池辺にはなかったというか執着しなかったのです。
ナンバリングによって呼称された作品群がその事を物語っています。
徹底した実験主義者だったのです。
西沢大良氏はキヨシの「立体最小限住居」と増沢洵の自邸「最小限住居」を例に
とって、同時代の小住宅として比較検討しています。(*9)ここで西沢氏は増沢○
池辺×といった論調を展開しています。(この場合の増沢を清家と置き換えても読める
論考である。)しかし、一概に比較はできないとも思うのです。
見据えている視点があまりにも違うように感じるのは私だけでしょうか。
おそらくキヨシは反論を受けることも想定内でわざと意識的に増沢やきよしとは違う
方法を取っていたはずです。50年代の小住宅設計を通じてモダンアーキテクチャー
が抱えている課題を工業化と生産性と捉えて、それらを浮彫りにして60年代に
入ってからはそれらを体系化することに力を注いでいました。建築そのものよりも
建築を構築していくシステムに強い関心を示していたキヨシの作る住宅は住みやすさ
とは程遠く、居心地といったようなフレーズからはきっぱりと切れていました。
切れていること。このフレーズもまたモダニズムの重要なフレーズなのです。地縁、
血縁といったしがらみだらけの社会システムからきれいに切断されて近代家族として
ひとつの住まいで完結できるのがモダン住宅であるのでしょう。(*10)
キヨシはこの後に訪れる高度経済成長を予測し、住まいや建築が社会とどうシンクロ
しながら変わって行き、その結果どのような弊害をもたらすかをイメージ出来て
いたんじゃないでしょうか。工業化、計量化の果てに見出される長所と短所、それを
出来る限り早い段階で立証し短所を改めていかなければならない事に警鐘を鳴らす
意味で徹底的に建築設計の工学化に猛進したのだ。現在進行形の建築、都市、生活、
環境といったものが抱えている問題点を予測したうえでの実験住宅だったのでは
ないのでしょうか。
昨年2009年はキヨシの没後30年でした。キヨシが投げかけたテーマが何であったか
を解読するには難しい面が多い。それほどに難解な建築家であったのですが、
現在改めて建築家・思想家として彼を再評価することは環境の時代と言われる
21世紀の建築を考える上で重要なテーマになりうると思うのです。
-続く-
次回Vol.4にてふたりのKIYOSHI完結!
*印の内容について補足をブログ「普通の家 普通の暮らしを求めて」に
記していますので、そちらも併せてご覧ください!
→→→“きよし”と“キヨシ”を読み解くヒント(その3)