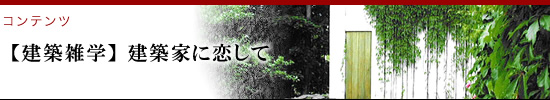
序
戦後小住宅の時代と呼ばれた時期があった。この時期を生活改革の時代の
到来と捉えて思潮をリードする建築家たちが、新時代の住宅に普遍的な性格を
求めて、斬新な試みを大胆に展開した小住宅の設計を積極的に行った時代である。
(*1)そもそも時代と言うには短すぎて第二次世界大戦後間もなくの1950年代
前半のたかだか僅々6年ほどの間に過ぎないが、日本の建築史において実に
濃密重要な時期であることはいうまでもない。住宅政策開始と工業化住宅への
試みがこの時期の住宅建築の重要ポイントであり、文字通り20世紀の前半と
後半の住宅変貌の結節点を、この建築家たちの小住宅時代と捉えることができる。
この頃に増沢洵、広瀬鎌二らと並んで住宅設計をリードしたひとりに清家清がいた。
清家は矢継ぎ早に「森博士の家」「斎藤助教授の家」「宮城教授の家」「私の家」と
いう一連の傑作を送り出し、日本の住宅の伝統と近代建築との結合に成功した。
これらの作品は当時の建築界の注目するところとなり訪日していたグロピウスが
絶賛(*2)し、その後清家を自らの事務所TAC(*3)に招聘するまでになる。
国立大学の教授でありながらテレビCM(*4)に出演するなど物議を醸しながらも
広く世間に知られ、著作も多く広く市民権を得た建築家の第一世代と言えるだろう。
そして、清家と同じ時期にもうひとり積極的に住宅建築を世に送り出した「KIYOSHI」
がいた。池辺陽は戦後モダニズムの精神を最も純粋なかたちで表現し生き抜いた
建築家と言っていいだろう。設計の手法を徹底的に科学化して来るべき近代に対応
する事を試みた新時代創造主であったと言える。
しかし早逝したことも手伝ってか人々の記憶から遠ざかり、清家ほど現代に於いては
その知名度は高くないのかも知れない。しかし清家を論じるとき、この池辺なしには
論じ切れないところがあり、またその逆も叱りである。同じ「KIYOSHI」で互いに
交流もあり仲も良かったというふたり。反面、建築家としてのスタイル・スタンスは
対極にあった。
同じ時代を生きたふたりの「KIYOSHI」は近代建築、モダンアーキテクチャーを
どのように捉えていたのだろうか。
清家と池辺という座標軸に沿って日本のモダンアーキテクチャーの本質を探るべく、
このコンテンツ[建築雑学]の論考では融通無碍でソフトだった清家をひらがなの
“きよし”で、頑なにストレートだった池辺をカタカナの“キヨシ”というイメージで表し、
ふたりの生き様、建築様を通しての近代建築の意味とモダニズムの精神を紐解いて
見たいと思います。
次回は先ず、“違いがわかる男”清家清さんに関して述べてみたいと思います。
お楽しみに!
- 続く -
*印の内容について補足をブログ「普通の家 普通の暮らしを求めて」に
記していますので、そちらも併せてご覧ください!
→→→ “きよし”と“キヨシ”を読み解くヒント(その1)